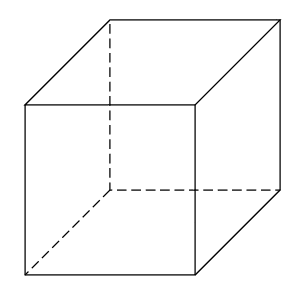
現代の自然科学、とくに地球科学では、質量保存の法則にもとづいて、物質循環を論じる。 たとえば、「水収支」は、化学変化による質量変化が移動による質量変化よりも相対的に小さいことを前提として、 水 (H2O、固体・液体・気体の3相をふくむ) にかぎって質量保存を応用したものである。
人びとは、古代から、明確に質量保存ではなかったがそれに近い考えにもとづいて、 物質循環や物質収支を論じてきた(はずだ)。
質量保存の法則が科学の知見として確立したのは、 ラヴォアジエ (Lavoisier, 1743-1794) の燃焼の実験をはじめとする、18-19 世紀の化学の進展による。 そのころから質量保存は化学実験装置でおこることに適用され、 さらに (19世紀末ごろに発達した) 化学工業プラントにも適用されてきた。
地球科学に適用されたのがいつごろか、わたしにはまだ確認できていない。 水循環の考えは比較的古くからあった ([物質は循環しているのか。 たとえば、雨の水はめぐりめぐってまた雨になるのか。] 参照)。 それ以外の物質循環の考えは、 ソ連 (ウクライナ) のヴェルナツキー (Vernadsky, 1863-1945) が、1920年代、地球化学 (geochemistry)、 さらに「生物地球化学 (biogeochemistry)」あるいは「生物圏 (biosphere)」の科学を提唱し、 そのような考えが数世代をかけて科学者のあいだに普及していったのだと思う。
1970年代ごろから、「気候システム (climate system)」および 「生物地球化学サイクル (biogeochemical cycles)」の考えかたが発達してきた。
「システム (system、系)」ということばは、とても多様な意味につかわれている。 ここではひとまず、熱力学の用語としての「系」を考える。 これを定義するのもむずかしいが、 ひとまず重要なことは、系内と系外の境界を明確にしていることだ。
質量保存の法則と エネルギー保存の法則 = 熱力学第1法則 (1840-50年代に定式化された) は、 まず、系の境界をよこぎる物質やエネルギーの出入りがない系 (ここでは「孤立した系」とよぶことにする) について定式化された。 孤立した系では、時間とともに、系のもつ質量も、系のもつエネルギーも、変化しない。
(宇宙全体でなく) 宇宙の部分を系として考えるならば、系の境界をよこぎって物質が出入りすることも 考えにいれる必要がある。 「系」を、ここでは箱のようなものと考えよう。 この図を、3次元の直方体の箱の見取り図だと思ってほしい。
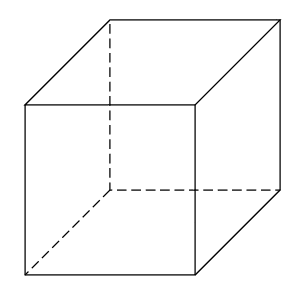
この箱の中の質量の「たまり」 X と、 箱の壁 (であるかのように仮想された境界) をよこぎる質量の「流れ」 F を考える。 流れが継続していることを想定するので、 流れの量は単位時間あたりに動く質量としてあつかう。 時間を t とする。d( )/dt は時間による微分である。 つぎの「X」を、「質量」と読みかえてみてほしい。 (エネルギー保存の法則を考えるときには、「エネルギー」と読みかえる。)
「開いた系 (開放系)」「閉じた系 (閉鎖系)」という表現があるが、 その意味は、現代の科学者のあいだで、統一されておらず、 エネルギーの出入りはあるが物質の出入りはない系を、 「閉じた系」とよぶ人と、「開いた系」にふくめる人がいる。 わたしは「閉じた系」という表現をさけることにする。 (なお、物質の出入りがあればエネルギーの出入りはかならずある。)
地球の大気・海洋・雪氷・陸面をあわせて「系」と考えることができる。 1970年代から、これを「気候システム」 (climate system) と呼ぶことがしだいにふえてきた。
【「陸面」に、陸のどのくらいの深さまでふくめるかはむずかしい。 正確ではないが、陸上の水 (湖沼、河川、土壌水分など) と土壌はふくめるが、 岩石はふくまない、というイメージでとらえておいてほしい。】
気候システムは、近似的には、物質の出入りがない系である。 それを部分にわけると、部分のあいだで物質のやりとりがある。 すくなくとも、水のやりとりは無視できない。
また、気候システムは、日変化や年変化をならしてみると、おおまかな近似では、 定常状態にある系とみなすことができる。 質量のたまりの量も、流れの量も、時間とともにかわらず、 流れの量は、たまりにとっての質量の収入と支出がつりあうようになっている。
「気候システム」よりややおくれて、 「全球規模の生物地球化学サイクル (global biogeochemical cycles)」の考えが発達した。 (いくらかは、かつてのヴェルナツキーの考えからの発展でもあるだろう。) Cycles が複数になっているのは、たぶん、元素別に「炭素循環」「窒素循環」などを論じるからだと思う。
つぎの図には、上側に気候システム、下側に生物地球化学サイクルがしめされている。 あわせたものを「地球システム」ということもあるが、その用語は地球内部もふくんだものをさすこともあるので、 区別して「地球表層システム」のようにいうこともある。 この図がふくまれた文書では「地球システムのうち流体・生物のプロセス」のような表現がされていた。
この図で、現実には同じ空間をしめている海洋や大気が上下にそれぞれしめされているのは変だが、 人間が、とくに近代科学の方法によって、自然を認識するうえでの能力の制約を反映している (とわたしは思う)。 ほんとうは多様な物質が空間に (分子までこまかく見なければ) 連続的に分布しているのだが、 「気候システム」という観点は、物理を背景知識とし、物質の種類わけは単純化し (たとえば大気は水蒸気と「乾燥大気」、 海洋は水と「塩物質」のそれぞれ2成分)、空間分布はかなりくわしく見る。 「生物地球化学サイクル」という観点は、化学を背景知識とし、物質の種類をくわしく区別して認識し、空間分布のあつかいはおおまかだ。 しだいに、気候システムを考える際に考慮する成分の種類がふえ、 生物地球化学サイクルを考える際に考慮する空間分布がくわしくなってきて、 両者の考えかたは融合してきた。
「気候システム」や「地球表層システム」をなぜ「システム」というかについては、 明確な定義のようなものはないと思うが、 わたしは、質量やエネルギーの保存則にもとづく「流れ」と「たまり」からなる系というとらえかたと、 制御工学からきた「フィードバックシステム」というとらえかたが複合したものだと考えている。
「システム」については、「生態系」のところでまた考えたい。
物質やエネルギーの流れのある準定常系という考えは、 日本の文化圏にむかしからある発想に近いと思う。 そこにはあきらかに仏教を通じたインド文明圏の影響があるが、 その伝来前から似た発想があったのかもしれない。
たとえば、『方丈記』 (鴨 長明, 1212年) の冒頭。
ゆく川の流れは絶えずして、しかも もとの水にあらず。
よどみに浮かぶ うたかた は かつ 消え かつ 結びて、ひさしく とどまりたる ためし なし。
第2文は、泡が、それを観察する人間にくらべて短い時間のあいだに、生成・消滅したり、位置を変えたりすることをのべている。 これも、第1文の「もとの水にあらず」も、 「諸行無常」、つまり、この世界 (宇宙) のものごとはいずれも永久ではなく かぎられた時間だけ存在するものだ、と とらえられることが多い。
しかし、わたしは第1文の「絶えずして」にも注目したい。 水は入れかわっても、川という構造は持続しているのだ。 流量の変化はあるだろう。つまり「定常」とはいえないだろうが、「準定常」とはいえるだろう。
西洋文明圏にも、似た発想はある。 古代ギリシャの紀元前6~5世紀のヘラクレイトス (Herakleitos) の 「万物は流転する」 (panta rhei) と要約される議論は「もとの水にあらず」と同様である。 しかし、ヘラクレイトスの論としてつたえられるものでは、川の持続性にあたる論点はないようだ。
ヘラクレイトスが言ったことを確認するため、廣川 (文庫版 1997) の本を見た。
ヘラクレイトスのことばは、他の本にとりこまれた断片だけが残っているのだが、 川の水がでてくるのは、つぎにあげる断片である。 (廣川 訳。番号は Diels & Kranz の 1966年版の本でつけられたもの。)
91 は、「(人は) 同じ川に二度入ることはできない」と言っている。 他方、12は、水はちがうと言いながら、「同じ川に入る」ことはみとめている。 しかし「ヘラクレイトスは川の持続性をみとめたこともある」と主張できるほど 明確ではないと思う。 49a の意味はわたしにはよくわからないが、 もし、12や91と関連した話題だとすれば、 ある時の川と別の時の川とが「同じ」であるとも「同じでない」ともいえる、 という意味かもしれないと思う。 わたしの暫定的結論としては、 ヘラクレイトスの思想に川の持続性にあたるものがふくまれていたかどうかは、どちらともいえない。
なお、ヘラクレイトスが、(宇宙のうちのそれぞれの物はうつりゆくとしながら) 宇宙全体の秩序は変わらずたもたれると考えていたことが、 つぎの断片からわかる。