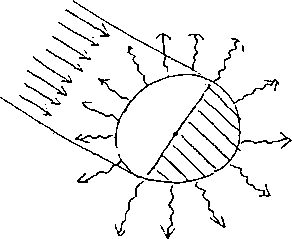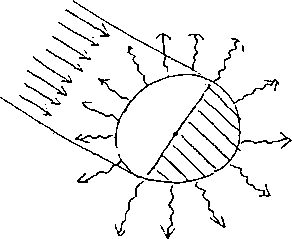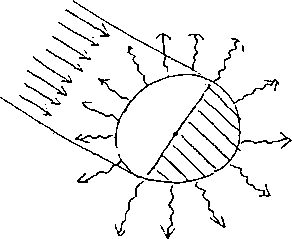気候システム論
地球全体としてのエネルギーの出入り: 太陽放射と地球放射
地球全体(大気を含む)のエネルギー収支の0次元・定常的考え方
定常 ... d(エネルギー貯留量)/dt = 0。
したがって、単位時間あたり流入 - 単位時間あたり流出 = 0。
【定常を前提としない考えかたは、
「0次元エネルギー収支モデル」のページ参照。】
0次元 ... 空間分布による違いを無視し、地球全体がひとつの温度 T をもつと仮定
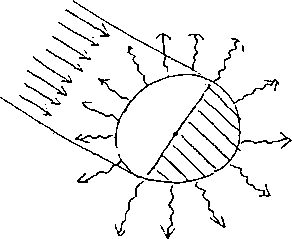
単位時間あたりエネルギー流入 = 単位時間あたりエネルギー流出
吸収する太陽放射 = 射出する地球放射
π r2 × (1 - αp) × S0 = 4π r2 × σ T4
- S0: いわゆる「太陽定数」。1360 W/m2 (観測にもとづくおよその値、4桁めは無効数字)で一定と仮定。
- αp(惑星アルベド): 地球が太陽放射を反射する割合、0.31 (同)で一定と仮定。
- 地球の出す放射を温度Tの黒体放射と仮定。
単位面積あたり・単位時間あたりのエネルギーとして σ T4 (σはStefan-Boltzmann定数)。
なお、このTを地球の有効放射温度といい、Teと書くことがある。
- r: 地球半径 (つりあいの式の両辺を地球表面積で割れば消去される)。
このT(地球の有効放射温度)は約254 K (-19℃)となり、
だいたい対流圏中層の気温に対応する。
地上気温は全球平均で約14℃ (287 K)で、有効放射温度よりも高くなっている。
この理由は、地球大気中に地球放射を吸収・射出する物質があることで説明される
([温室効果の基本の回]に続く)。
0次元ではあるが大気と地表面を分けたエネルギー収支の数値は
[別ページ]で示す。
地球全体(大気を含む)のエントロピー収支の0次元・定常的考え方
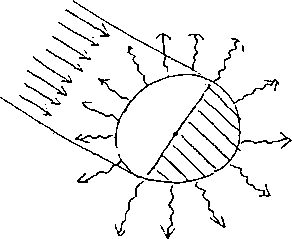
エネルギー収支
吸収する太陽放射エネルギー = 射出する地球放射エネルギー
Q1 = Q2
吸収放射のエントロピー + 地球でのエントロピー発生 = 射出放射のエントロピー
Q1 / T1 + (発生量) = Q2 / T2
- T1 ≒ 5800 K、 T2 ≒ 254 K
- 「エントロピー発生」には次のものを含む(が、それだけではない)。
- 熱機関的に力学的(運動、位置)エネルギーを生み出すときに発生するもの
- 力学的エネルギーが摩擦で内部エネルギーになることにともなうもの
放射に伴うエントロピーの流れは、
上記のようにエネルギーの流れを温度で割ったものとする考えのほかに、
その4/3倍とする考えがある。
わたしはどちらが正しいか決められないが、授業では前者の考えに従っておく。
[ブログ記事]参照。
地球のエントロピー収支の定量的なことは、上の概略的な値以外はまだよくわかっていないが、
理論的には小澤 久 博士(広島大学, もと地球フロンティア)の研究によりだいぶ整理された。文献はOZAWAほか (2003)。
(小澤 2005もあるが、ここでの議論に直結しない。)
0次元ではあるが大気と地表面を分けたエントロピー収支は[別ページ]で論じる。
文献 (エントロピー収支について)
- 小澤 久, 2005: 気候とエントロピー。
パリティ, 20 (No. 8), 24 - 31.
- Hisashi OZAWA,
Atsumu OHMURA,
Ralph D. LORENZ &
Toni PUJOL, 2003:
The second law of thermodynamics and the global climate system:
A review of the maximum entropy production principle.
Reviews in Geophysics (American Geophysical Union),
41, 4/1018, 24 pp.
2007-05-07; 更新(最新) 2012-05-10
増田 耕一