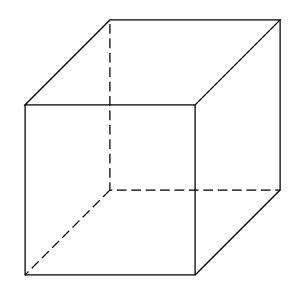
日常用語でいう「重さ」は、 数量として考えると、実は複数の意味を含んでいる。
たとえば、炭を燃やすと、わずかな量の灰を残して消えてしまうように思われる。 しかし、気体をのがさないようにして重さをはかり、 気体の性質を調べることによって、 「炭の炭素が空気中の酸素と化合して、二酸化炭素となって空気中に出ていった」 と解釈するべきであることがわかった。 反応前後の炭素、酸素、二酸化炭素を合わせて考えると、質量は保たれている。 この認識を1人の科学者の仕事で代表させるとすれば、 ラヴォアジエ (Lavoisier) の1770年代の仕事だろう。 このような実験による経験が重ねられた結果、 測定していない場合でも、質量保存が成り立っているにちがいないと認識されるようになってきた。
「質量保存の法則」の「保存」は、 たとえば「文化財の保存」などの文脈での意味とはちがった、物理系の科学での意味に使われている。 一般に通じる日本語表現のうちでは「不生不滅」に近い。 質量という量は、かってに生じたり、かってに消えたりしないで、持続する、ということだ。 ただし、これを「質量は時間とともに変わらない」と表現してよいのは、 注目する「系[けい]」が、質量の出入りのない系であるばあいにかぎられる。 「系」の概念は単純ではないが、ここでは箱のようなものと考えよう。 この図を、3次元の直方体の箱の見取り図だと思ってほしい。
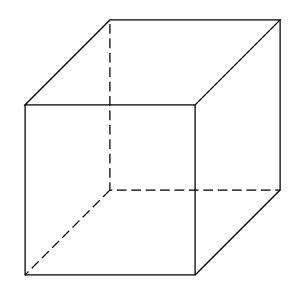
箱の壁を通過する質量の出入りがないならば、 「質量の保存の法則は、箱の中の質量は時間とともに変わらない」でよい。 箱の中で、固体・液体・気体のあいだの相変化や、化学反応があっても、これはなりたつ。
地学で、大気・水圏全体をひとまとめにひとつの系としてあつかうときは、 系とその外とのあいだの質量のやりとりは、厳密にいえばあるが (隕石がとびこんできたり、水素がぬけていったりする)、 ないと近似できるので、 大気・水圏全体の質量は時間とともに変わらない、とみなすことができる。
しかし、地学では、地球を部分にわけて、それぞれの質量の変化を考えることが多い。 たとえば、大気を、緯線・経線で、ます目にわけて、それぞれの箱の中の質量の変化を考える。 このとき、箱の壁は仮想的な壁にすぎず、壁をとおりぬける空気の流れ(風)がある。 そのようなばあいも質量保存の法則はなりたつが、それは 「箱の中の質量は時間とともに変わらない」というものではない。 「箱の中の質量の変化は、箱の壁をとおりぬける質量の正味の流入量にひとしい」となる。 ただし、「正味の流入」とは、流入を正、流出を負として合計したものである。 質量は不生不滅なので、質量の変化の理由は、箱の境界からの出入りにかぎられる。 これがわかっていると、箱の中の質量の変化か、箱の壁をとおりぬける質量の流れか、 一方の数値がわかれば、他方の数値を推論で知ることができる。
特殊なばあい(「定常状態」という)として、箱の壁をとおりぬける質量の流れがあるにもかかわらず、 箱の中の質量が時間とともに変化しない(ことがわかっている)ばあいがある。 そのとき、箱の壁をとおりぬける質量の流れは、正味でゼロである、 言いかえると、質量の流入と質量の流出がつりあっている、ということができる。 地学では、質量保存の法則を、このような形でつかうことが多い。
数式のような表現で書きなおすとつぎのようになる。ひとまず「量X」とは「質量」だと思って読んでほしい。
量Xの保存が成り立つとは、 孤立した(量Xが出入りしない)系では、Xが時間とともに変化しないことであり、 開いた(量Xが出入りする)系では、Xの時間変化がXの正味の出入り(入り - 出)に等しいことである。
地学では、厳密に定常ではないが、近似的に定常 (準定常) であるような系をあつかうことが多い。
ここで思いだすのは、『方丈記』の冒頭、 「ゆく川の流れは絶えずして、しかも もとの水にあらず。」だ。 橋の下を流れる川を見ていたとしよう。 橋の真下にある水はつねに入れかわっている。 水の流量 (単位時間あたり通過する質量) も、厳密には一定ではないだろう。 しかし、「流れが絶えない」ということは、流量が けたちがいに小さくならないこと、 つまり、(ある意味で) 同程度の流量が持続していることを意味するだろう。 「流れは絶えず」は、動的で持続性のあるシステムを形容する表現なのだと思う。